もろ蓋?こうじゅうた?麴蓋?なの、もろ蓋について
お餅などを入れておく昔ながらの木箱の写真を掲載しています。
こうじゅうたと呼んでいた記憶がありますが。もろ蓋(もろぶた)が一般的なようです。
呼び名も色いろあるようでこうじゅうたんや麹蓋(こうじぶた)・麹いたなどと呼ぶ地方もあるようです。
微妙に違うものなのかな。
スポンサーリンク
もろ蓋(もろぶた)について
- 「もろ蓋」は調理器具・発酵用具の一つで、長方形の木製の箱のような形状をしています。
昔ながらのもろ蓋は木製なので、お餅や中の食品に適度な湿度が加わり良い感じで保存できます。 - 漢字では「麹蓋(こうじぶた)」とも表記され、特に日本酒の醸造工程、麹を扱う場面で使われる道具です。
- また、餅や饅頭を入れたり、押し寿司などのあらましに使われることもあるようです。
- 最近はプラスチック製のものももろ蓋と言われています。
🔍 用途・背景
- 日本酒の「麹造り」の際、蒸し米に麹菌をまぶして発酵を進める「盛り」の段階で、熱を帯びた米麹を管理するためにこの“箱”が使われます。
- 木製であることが多く、たとえばスギ材を使った「縦45cm×横30cm×深さ5cm程度」のものがあります。
- また、食品加工・餅つき・和菓子作りなど、発酵や蒸し・熟成など“温度・湿度・風通しを気にする工程”で使われることもあります。
🔍昔ながらのお餅の木箱はこうじゅうた
その昔こうじゅうたって呼んでいたような気がします。
年末に自宅でお餅をついてこうじゅうたに並べる、、、
古いもろ蓋はメルカリなどで探してみるとたまに出てます。
↓↓↓
メルカリでもろ蓋をチェック



サイズ:約52×32×5.5cm
内側サイズ:約43×29×5cm
材質:木製
注意:経年の傷みやネズミに齧られた跡などあります
こうじゅうたはいくつかありますが、それぞれ傷み方が違います。
これもレトロなあじわいというものでしょう。
🔍大きいもろぶた
サイズ:約65×35.5×12cm
内側サイズ:約58.5×32×10cm
蓋サイズ:約65×39cm
材質:木製
注意:虫食いあり
蓋はやや大きめです。
左右に取っ手というか出っ張りがあります。
もろ蓋の選び方(木製/プラスチック)
・材質の違いと特徴
-
木製のもろ蓋:例えば「国産天然杉100%」を使ったものもあり、板厚・仕上げ・手作りの職人加工品もあります。
-
長所:天然木の風合いや通気・吸湿性が良い場合がある。発酵・麹造りなど“木の呼吸”を活かした工程に合う。
-
短所:水分・汚れ・カビ・臭いが付きやすい。重さや価格もプラスチックより高めのことが多い。
-
-
プラスチック製のもろ蓋/番重型容器:汎用コンテナ扱いのものもあり、材質にポリプロピレン(PP)などが使われている例も。
-
長所:軽い、価格が安い、洗いやすい/乾きやすい、衛生管理もしやすい。
-
短所:木のような自然の通気・湿気調整機能には劣る。発酵・麹造り等にはその “木ならでは” の良さが失われる可能性あり。
-
・用途に応じて選ぶポイント
- 発酵・麹造りなど 温度・湿度・風通し・木の香り・微生物環境 が影響する用途 → 木製のもろ蓋が好まれる傾向あり。
- 餅箱・運搬箱・製麺・食品加工・保管といった 汎用・頻用・衛生重視 の用途 → プラスチック製もろ蓋/番重が選びやすい。
・サイズ・形状・蓋付きかどうか
- 「蓋付きであれば“もろ蓋”、蓋無しなら“番重”」という分類もあります。
- 深さ・内寸・材質厚み・重ねられるかどうか・蓋の密着具合なども選ぶときにチェックしたい。
- 表示や仕様(木の種類/仕上げ/国産/加工・手作り/サイズ)を確認すると安心です。
もろ蓋はメルカリなどで探してみるとたまに出てます。
↓↓↓
メルカリでもろ蓋をチェック
・まとめると
「発酵用・伝統的な工程なら木製を、日常使いや汎用・メンテ重視ならプラスチックを」という選び方が目安です。
それで…この方向性で大丈夫でしょうか?次に「手入れ・衛生管理」について進みましょうか?
もろ蓋の手入れ・衛生管理
食品を扱うことになるので、どうすれば長く・安全に使えるか を考えましょう。
・衛生の基本(食品加工・発酵に共通)
- 食品加工・発酵工程では、器具・器材・道具の清掃・殺菌・乾燥が重要です。湿気・栄養・温度が揃うと菌(望ましい菌も雑菌も)が増殖しやすいため。
- 使用後には、残りの食品カスや水分をすぐに取り除くこと。特に木製の場合、水分が残るとカビ・臭い・劣化の原因になります。
・木製もろ蓋の手入れポイント
- 使用後はまず軽く布などで表面を拭き、場合によってはぬるま湯で洗浄(洗剤使用時は木が痛まないものを選ぶ)→そのあとよく乾燥。
- 乾燥時は風通し良く、直射日光や極端な高温・高湿を避ける。木が反ったり割れたりしないように。
- 定期的に木の表面を軽くサンドペーパーで整えたり、必要であれば無害な木材保護剤(食品加工対応)を薄く塗ることも。
- 汚れ・染み・臭いが強くなった場合は、重曹+お湯で軽く浸してから清掃 → ただし完全に水没させる長時間は避けた方が無難。
・プラスチック製・番重型のメンテナンス
- 汚れ落ちが良いため、洗剤使用→すすぎ→乾燥という流れが比較的ラク。
- 傷・ひび割れがあるとそこに汚れ・菌・臭いが溜まりやすいので、定期的に点検。使えなくなったら交換も検討。
- 高温・冷凍・紫外線が当たる環境だとプラスチックが劣化しやすいため、その点も注意。
・共通の注意点
- 蓋の密閉性・通気性のバランスを用途に応じてチェック。発酵用途なら通気+蓋ありが重要。
- 道具・器具として使うなら、製造・保管環境が衛生的か(掃除・換気・温湿度管理)も考慮。
- 木製器具だと「木特有の微生物棲みつき」がゼロではないため、使用用途(食品/発酵)と材質・環境をきちんと考えて。
・実際によくある悩み&そのフォロー
「でも、それって毎回手入れが面倒なんじゃ…?」
→ そう感じる方も多いです。ですが、例えば木製を選んだなら「毎回軽く拭くだけ」「使ったら即乾燥させる習慣」をつけるだけでも劣化リスクがグッと下がります。
「プラスチックだと味や雰囲気が出ないからちょっと…」という声もありますが、衛生性・メンテ性を優先したいなら十分有力な選択肢です。
もろ蓋をDIY!作り方情報
もろ蓋は基本的に木製が多いので自分で作ってみるのもいいかもしれません。
材料はホームセンターで簡単に手に入りますからね。
・メリット
- サイズぴったり・自分の用途(発酵量・スペース)に合わせて作れる。
- 木材の種類・厚さ・仕上げにこだわって「理想のもろ蓋」を作ることができる。
- 愛着が湧く/見た目・雰囲気も自分好みに。
・デメリット/注意点
- 木工スキル・道具・時間が必要。特に「木の反り/ヒビ/接着部のガタつき」などを防ぐ設計が求められる。
- 材質・仕上げ次第では衛生管理が難しくなる(木が汚れを吸いやすい)。
- 完成後のメンテナンスが市販品より手間になることも。
・簡単な作り方の流れ
- 材料選び:例えば「天然杉/桧/檜」など、食品用途向けに適した木材を選ぶ。例として「飫肥杉のもろ蓋」も紹介されています。
- サイズ設計:用途(何kgの麹・餅・食品を扱うか)に応じて長さ・幅・深さを決める。例:縦380 mm×横190 mm×深さ48 mmというサイズ例あり。
- 組立:底板+側板+蓋を用意。木材を接ぎ→ビス・木ダボ・接着剤などを使いしっかり固定。蓋が密着するか、持ち運び・重ね使いできるかも検討。
- 仕上げ:木材の表面をサンディングして滑らかにし、食品用途に対応した木材保護処理(オイル仕上げなど)も検討。ただし発酵用途ではあまり塗り過ぎない方が「木の呼吸」を妨げないという声も。
- メンテナンス設計:使いやすい寸法・重さ・持ち手・重ね積み可否など。将来的な清掃・乾燥を見越して構造を考える。
・DIYでのポイント・工夫
- 側板の厚みを一定以上(例:15 〜 20 mm)にして反りや割れを防ぐ。
- 底板に木目方向を考えて配置し、荷重・湿気の影響を分散。
- 持ち運びしやすいよう“若干小さめ”サイズにすることで使いやすさアップ(例:先のサイズ例のように通常より浅め)
- 水洗い・乾燥・風通しがしやすい設計(脚をつける、小さな隙間を設けるなど)を考える。
・こんな人にDIYがおすすめ/そうでない人
- おすすめ:木工が好き、サイズにこだわりたい、自分で仕上げをしたい、味・雰囲気重視の発酵プロセスを行いたい人。
- あまりおすすめではない:手入れの手間を省きたい、衛生管理重視、すぐ使いたい/汎用で十分という場合は市販品の方がラク。
注意点・まとめに向けて
最後に、使ううえで「失敗しがちな点」&「押さえておきたいこと」を書いておきます。
- 木製を選んだのに「清掃/乾燥がおろそか」でカビ・臭いが出てしまった…というケースはよくあります。
- プラスチックを選んだのに「通気が悪く蒸れた/臭いがこもった」ということも。用途によって通気設計を意識。
- 蓋と本体の密着具合も重要。発酵の際、過度に密閉しすぎるとガス/湿気がこもる場合もあるため。
- DIYするなら「使いやすさ(重さ・持ち運び)」「清掃・乾燥性」「素材の処理(仕上げ・木材保護)」をちゃんと設計すること。
- 衛生管理として、道具/環境(温度・湿度・風通し)を整えることが、道具選び以上に結果を左右するという点も押さえておきましょう。







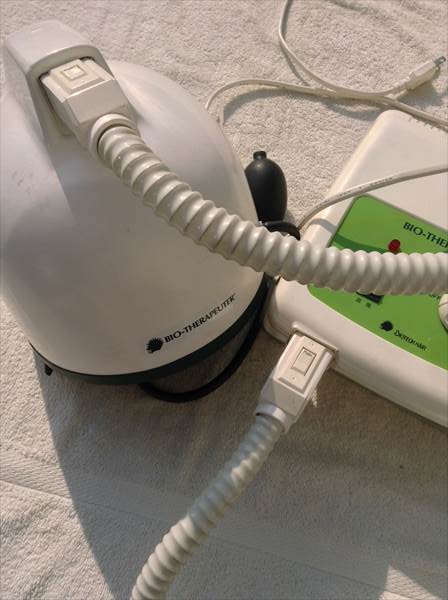






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません